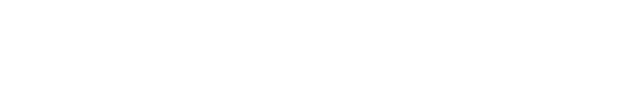逆流性食道炎
逆流性食道炎について
胃食道逆流症(Gastro Esophageal Reflux Disease : GERD)とは強い酸である胃酸や胃の内容物が食道側に逆流することで症状を起こす疾患です。
食道粘膜に炎症を起こす場合(逆流性食道炎)と起こさない場合(非びらん性胃食道逆流症)があります。
この疾患にかかると健康な人に比べて日常生活の質(QOL)が低下してしまいます。
食生活の欧米化や高齢化、そして、ピロリ菌感染の患者数が減少していることから、近年増加傾向の疾患です。
現在では成人の10~20%がこの病気にかかっていると推測されています。
逆流性食道炎の原因
食道裂孔ヘルニア(胃が口側に上昇している状態)、肥満、高脂肪食、亀背、暴飲暴食などが原因と知られております。
食道は胃酸などに対する防御機能は弱く、食道に逆流した胃酸によって食道粘膜は容易に傷ついてしまいます。
胃の手術をした場合に起こりやすくなったり、また、便秘などの消化管の中身の停滞により逆流症状が起こったりすることもあります。
ストレスにより症状が悪化することもあります。
逆流性食道炎になりやすい人
- 夕食の時間が遅く、食後すぐに就寝する人
- 油ものをたくさん食べる人
- 肥満
- 高齢者
逆流性食道炎の症状
胸やけや胸のむかむか感や胸部の痛み、酸っぱいもの・苦いものが上がってくる感じがすること(呑酸)などがよくある症状です。
食後や朝起きた時などに自覚すること多いです。
時には虫歯や不眠の原因となることや長期的に継続する咳の原因となっていることもあります。
逆流性食道炎の検査・診断
問診で症状を確認し、診断します。
胸やけや呑酸などの症状がある方や症状がなくても内視鏡検査で食道粘膜の障害などを認めた場合には胃食道逆流症の診断になります。
内視鏡の検査は必須ではありませんが、内視鏡検査を行うことで現状の評価や治療方針が立てられることがあります。
逆流が起こっている原因の検索のために、レントゲン検査やCT検査などを行うこともあります。
通常の治療でも治療が難渋する場合には食道の動きや酸性度などを測定する検査を専門施設で行うこともあります。
逆流性食道炎の治療・予防
- 生活習慣の改善
- 薬物療法
- 手術
生活習慣の改善に加えて、胃酸をおさえるよう薬を使用します。
最近では、プロトンポンプ阻害薬(PPI)と言われるものや、より強力に胃酸を抑えるカリウム競合型アシッドブロッカー(P-CAB)と言われる薬剤を使用することが多いです。
胃内に食物が長く停滞する場合には消化管運動改善薬や漢方薬を使用することで症状が改善することもあります。
ヘルニアが大きく症状が非常に強く、内服薬での改善が見込めない場合には、逆流が起こりにくい形に食道を形成する手術を行うこともまれにあります。
胃酸分泌抑制薬以外では、消化管の蠕動運動機能改善薬、粘膜保護薬、漢方薬などを用いることもあります。
生活習慣の改善
- 食べ過ぎ・飲みすぎしないようにする
- あぶらものの摂取を控える
- 就寝前3 時間以内の食事習慣を控える
- 増悪しうる食べ物:揚げ物、甘いもの、アルコール、チョコレート、コーヒー、炭酸飲料、柑橘類など
- 増悪しうる生活習慣:腹部の締め付け、重いものを持つ、前かがみの姿勢、肥満、喫煙など
- 寝るときにも枕を少し高くして横になることで逆流を予防できることがあります。
胃食道逆流症・逆流性食道炎の再発予防
上記に示すような食事習慣や生活習慣の改善を行うことで症状が軽くなったり、再発が起こりづらくなったりします。
もともと胃酸が強かったり、逆流が起こりやすい方もいらっしゃいますので、症状に我慢せず症状が始まりそうなときには予防的に治療を開始することが大切です。
まとめ
- 胃酸や胃の内容物が逆流することで起こる
- 食後や朝起きた時に多い
- 咳や虫歯、不眠などの原因になることもある