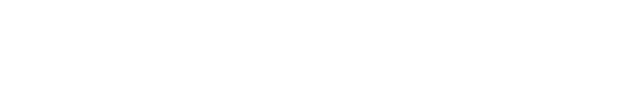機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアとは?
内視鏡検査やCT検査などの検査で器質的疾患(腫瘤や炎症)などがないにも関わらず、心窩部(みぞおち)を中心とした上腹部に様々な症状が出現する病気です。
その状態が長期的に継続してしまうときにこの病気と診断されます。
具体的にはみぞおちの痛み、不快感、胃がもたれる、すぐにおなかがいっぱいになってしまうなどの症状が起こります。
頻度
人口の20~30%に認めると推定されています。
機能性ディスペプシアの原因
胃の運動異常や胃酸の分泌異常や知覚過敏が直接関与していると言われていますが、胃酸やピロリ菌、生活様式や食事、遺伝的背景など多くの事柄が関係していると言われています。
何らかのストレスをきっかけとして症状が始まることが多いと言われています。
また、十二指腸に対する胃酸の影響が消化管の運動に影響を与えることもわかってきました。
機能性ディスペプシアに関わるもの
- 消化管の運動機能異常(弛緩異常)
- 消化管の知覚異常
- 消化管感染後の残存炎症
- 胃酸、ピロリ菌感染、精神的因子、食事・生活習慣
- ストレス耐性、遺伝子異常
機能性ディスペプシアの症状
つらいと感じる食後のもたれ感、食事中早期の膨満感、みぞおちの痛み、みぞおちの灼熱感などが週に1回以上おきるという状態が長期的に継続した場合に機能性ディスペプシアと診断されます。
症状が軽い場合には日常生活に支障が出るほどではありませんが、症状に対して我慢する状況になるため生活の質が低下します。
重症の場合には、体重減少が起こったり、学校や仕事に行けなったりすることもあります。
いつでも症状があるわけではなく症状も多彩ですので、診断が難しいこともあります。
機能性ディスペプシアの診断
一般的には胃カメラで食道炎や潰瘍や癌など、症状の原因となりうるような器質的疾患がなく、採血、採尿、超音波、腹部CTなどの検査でも明らかな原因がないことを確認し診断に至ります。
短期的な症状ではなく、長期的な経過で起こっていることも病気の診断には必要になります。
機能性ディスペプシアの治療
ピロリ菌が原因となることがあるため、ピロリ菌が住んでいるようであれば除菌治療をはじめに行います。
ストレスに対する消化管の過剰反応が原因になることも多く、ストレスを避けたりとストレスマネージメントを行うことが重要と言われています。
生活習慣や食事療法を行っても症状が継続する場合には、内服治療を行います。
心窩部痛や心窩部灼熱感が中心の時には、胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬の内服を1~2か月行います。
食後の腹満感やもたれ、早期満腹感、悪心、嘔吐、げっぷなどが中心の時には消化管運動機能改善薬を使用し治療を行います。
心療内科的な治療が効果を発揮することもあります。
経過
ストレスマネージメントや内服治療で症状が落ち着いた場合には、一度治療の中止を検討しますが、再燃する場合には治療の継続が望ましいです。
症状が治る患者さんが多いですが、再燃することも多い病気として知られております。
日常生活の注意点・再発予防
ストレスを避ける生活や規則正しい生活、消化器に負担がかからない食事習慣を行っていくことが大事です。
症状が出現しにくくなる生活習慣・食事習慣には個人差がありますので、ご自身にあった体調がよくなる習慣を見つけておくことも重要です。
まとめ
- みぞおちを中心とした上腹部の症状
- 痛み、もたれ感、膨満感、灼熱幹、食欲不振、嘔気など