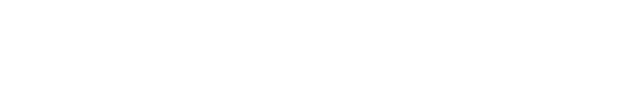便秘
便秘について
2023年のガイドラインで、「本来排泄すべき糞便が大腸内に滞ることによる兎糞状便・硬便、排便回数の減少や、排便を快適に排泄できないことによる過度な努責、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便困難感を認める状態」と定義されました。
わかりやすくまとめると以下のいずれかを認める場合になります。
- 出るべき量の便が出ていない(食べている量と排便量のバランスが悪い)
- 排便するときに苦労がある
※ただし、日常生活に影響が出ていなければ便秘ではない
食の欧米化や生活習慣の乱れ、ストレスなどにより増加傾向にあると考えられます。
年を重ねるごと腸管の蠕動は低下するため起こりやすくなり、また学校や仕事で便を我慢するという習慣からも便秘が起こりやすくなります。
高齢者や女性に多いと言われますが、どのような方でも起こることがあります。
QOLを下げるだけでなく、心血管疾患の発症・死亡リスクの上昇、パーキンソン病や腎疾患のリスクの上昇などに関与する可能性があると言われており、治療が必要です。
また、便秘により胃や食道の病気である機能性ディスペプシア(23%)や胃食道逆流症(56.7%)が一緒に起こることがあります。
便秘の症状
「便秘」自体が症状のことですので、便貯留の方に多い症状を記載します。
- 食後の腹痛、お腹が動く痛み(波がある)
- お腹の重い感じの痛み、脇腹~腰にかけての痛み
- 食事早期の満腹感、食が細くなる
- げっぷが多い
- おならが多い、おならが臭い
- お腹が張る、食後にお腹がすごく膨らむ
- お腹が激しく動くのを自覚するが出ない
- 便が細い、色が濃い、くさい
上記のようなものを認めた場合には一度ご相談ください。
便秘のタイプ
- 腸の動きが弱く便を運べないタイプ
- 腸が過剰な収縮をし、便をうまく運べないタイプ
- 大腸が詰まっている(大腸癌、腸重積など)タイプ
- 内分泌・神経・自己免疫などの病気によるタイプ
- 薬によるもの
など
大腸の検査・診断
問診・触診が非常に大事になります。
排便状態や腹部症状の出現の仕方によって便の貯留の状態や便秘のタイプを評価します。
また、腹部を触診することでガスや便のたまりを評価できます。
レントゲンや採血で状態を確認し、必要に応じで内視鏡検査を行います。
便秘の治療
生活習慣の改善や薬物療法が必要になります。ストレスを減らしたり、食生活の内容や時間を整えたりすることで改善することがあります。
しかし、便貯留の程度や加齢による影響により薬でのサポートを必要とすることも多いです。
食事療法
バランスの良い食事摂取は重要です。
グアーガム分解物(食物繊維)やキウイフルーツ、プルーン、オオバコなどは便通を改善させると言われております。
プロバイオティクス(腸内環境を整える生きた微生物)やプレバイオティクス(善玉菌の栄養源となる食物成分)やシンバイオティクス(その両方を組み合わせたもの)も便秘の改善が期待できます。
薬物療法
様々な薬があるため、それぞれに合った薬と容量を使用する必要があります。
- 緩下剤(便を柔らかくする薬):酸化マグネシウム、ラクツロースなど
- 膨張性下剤:ポリカルボフィルカルシウムなど
- 刺激性下剤:ダイオウ、センノシド、ピコスルファートなど
- 粘膜上皮機能改善薬:ルビプロストン、リナクロチド、
- 胆汁酸トランスポーター:エロビキシバット
- 腸管蠕動改善薬:モサプリドなど
- 漢方薬:大建中湯、麻子仁丸
まとめ
- 毎日排便があっても便秘のことがある
- 便を貯留することはQOLを下げるので治療が必要
- 生活習慣の改善や薬物でのサポートが重要