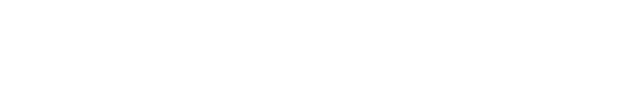下痢
下痢について
便の水分量が増加すると普通便→軟便→泥状便→水様便となり排便の回数は増加します。
急性下痢と慢性下痢(1か月以上持続するもの)に分けて考えます。
また、下痢の原理としては、①浸透圧性下痢(腸管内に水を集める)、②分泌性下痢(腸液がたくさん分泌される)、③腸運動異常性下痢(腸が過剰に動く)というように分類されますが、複合的に起こっていることも多いです。
下痢の原因
急性下痢の原因としては感染性腸炎があります。
春から秋にかけては細菌性、冬はウイルス性が多いと言われています。
そのほかにも炎症性の腸疾患や急性胃炎暴飲暴食、食物アレルギーなどでも下痢になることがあります。
慢性下痢の場合には機能性(過敏性腸症候群)や特殊な感染症、炎症性腸疾患などが原因のことがあります。
下痢の症状
小腸に感染した場合には水様便繰り返し、嘔気を伴うことがあります。
大腸に感染した場合には粘血便が出たり、疼痛が強かったりすることが多いです。
小腸の感染の場合、脱水症状が出現することがあります。
下痢の検査
脱水の程度を評価したり、炎症の度合いを評価するために血液検査を行うことがあります。
また、症状が長引いたり強い場合には便培養検査や内視鏡検査で評価することがあります。
下痢の治療・予防
感染性の腸炎の場合には基本的には抗生剤などは使用せず、水分や電解質を補充し、症状が改善するのを待ちます。
下痢止めを使用すると毒素や感染原因が停滞し、症状が長く継続してしまうことがあるので、基本的には使用しません。
吐き気止めや痛み止めを使用し、対症療法を行っていきます。
感染性腸炎の場合、周囲に移ることがあり、手洗いなど感染予防が重要になります。
特にノロウイルスの場合にはアルコールが効かないため、次亜塩素酸ナトリウムなどでの消毒が有効です。
感染以外が原因の場合には原因に対する治療を行う必要があります。
まとめ
- 感染性腸炎は夏、冬に多く周囲にうつる可能性がある
- 脱水に注意
- 慢性下痢の場合には大腸検査や便の培養検査が必要なこともある