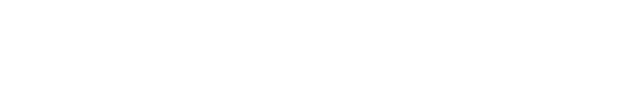ピロリ菌(ヘリコバクターピロリ)感染と萎縮性胃炎
ピロリ菌について
ピロリ菌とは胃の粘膜に住み着き、炎症や潰瘍を生じさせる細菌です。
ウレアーゼという酵素を作ることで胃酸を中和し、胃の中でも生きることができます。
多くの研究により、慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの原因になっていることが分かっています。
また、ピロリ菌が住んでいた場合には萎縮性胃炎という粘膜の変化が残り胃癌のリスクが通常の人よりも高いため、胃癌の早期発見のため定期的な胃カメラの検査が推奨されております。
ピロリ菌感染の原因
ピロリ菌は口から入り、免疫や胃酸が弱い幼少期に感染すると言われております。
浄水されていない水や家族内感染などが主な経路と考えられています。
胃癌の予防のため、ピロリ菌感染が分かった場合には除菌することが推奨されています。
親世代の感染率が低くなり、衛生環境もよくなったことから子供の感染率は低下してきています。
50代以上では40%が感染、40代では30%、30代では20%、20代では10%程度が感染していると考えられています。
ピロリ菌感染・萎縮性胃炎の症状
ピロリが感染していても萎縮性胃炎があっても無症状のことがほとんどです。
場合によっては症状を伴うような胃炎を起こしたり、潰瘍を繰り返したりすることもあります。
ピロリ菌感染の検査・診断
感染や除菌の成功を確認するには下記のような方法があります。
血中抗体検査
ピロリ菌に対する抗体の検査(抗体は長期に残ることもあり、除菌後の判定には使えない)
尿素呼気試験
呼気を集め、呼気中のウレアーゼを調べる検査
便中抗原検査
便中のピロリ菌を調べる検査
ピロリ菌感染の治療
通常は3種類の薬を7日間内服します。
1~2ヶ月程度期間を空けてから尿素呼気試験や便中抗原検査を用いてピロリ菌の確認を行います。
現在の薬では70~90%程度の方は除菌に成功します。
除菌に失敗した場合には、2次除菌に移ります。
3次除菌以降は保険適応がなく自費診療になります。
ピロリ菌感染の治療後について
ピロリ菌を除菌することで、胃癌の発生に関しては減少させることができますが、ピロリ菌未感染の人と比べると胃癌の発生率が高いので定期的な胃カメラを受けることが重要です。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍に関しては再発をほぼ抑制できます。
一部のリンパ腫やポリープなどについてはピロリ菌を除菌することで改善することが期待できます。
日常生活の注意点
一度除菌すると再感染する可能性は非常に低いと考えられますが、環境によっては大人になってから感染する可能性もあります。
アジアや南米に渡航し上腹部症状が出現した際にはご相談ください。
胃癌の予防
上記に記載した通り、胃癌の発生リスクがあるため定期的な胃カメラの検査を受けることが推奨されております。
1年に1回くらいの頻度で受けることが推奨されております。
最近では早い段階で胃癌を見るけることができれば、内視鏡で壁をそぎ取るような治療(ESD)をうけることができ、胃を切除しなくても済む場合があります。
まとめ
- ピロリ菌感染により胃癌発生のリスクが上がる
- ピロリ菌は一度除菌すれば、再感染する可能性は低い
- 除菌しても萎縮性胃炎は残り、定期的な胃カメラが必要