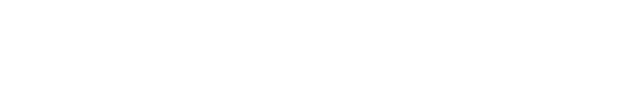マイコプラズマ感染症について
マイコプラズマ感染症について
マイコプラズマという細菌に感染することによって起こる感染症です。
小児や若い人に起こりやすいと言われており、報告の80%は14歳以下です。
1年を通じて見られますが、冬にやや増加する傾向があります。
以前は4年周期に流行すると言われておりましたが、最近ではその傾向はなく、2020年以降はやや多く、2024年は○○年の〇倍程度多かったと言われております。
原因
患者さんの咳の中に含まれていたり、患者さんと身近で接触したりすることで感染すると言われております。
家庭内や、学校の施設内で感染することが多いです。
感染から発症までの潜伏期間は長く、2~3週間と言われております。
症状
- 咳(乾いた咳→痰が絡む咳)
- 発熱
- 倦怠感
- 頭痛
- 声のかすれ
- 耳の痛み
- 咽頭痛
- 消化器症状
- 胸痛など
発熱、倦怠感(だるさ)、頭痛、咳などがあり、特に咳が特徴的です。
咳はやや遅れて(3~5日後)始まることもあり、乾性咳嗽と言われるような痰を伴わない咳で始まることが多いです。
その後、痰が絡むようになり、咳自体は長期にわたり(3~4週間)継続するのが特徴です。
通常の風邪との違いを判断するのが難しく、発症から3~4日経過しても症状が改善しない場合・咳が徐々に悪くなるにはマイコプラズマ感染の可能性を考える必要があります。
多くの場合はマイコプラズマ感染をおこしても気管支炎程度で済みますが、一部の人は肺炎になり重症化することがあります。
一般に小児の方が軽症ですむと言われております。
検査・診断
血液検査
白血球が正常なことが多く、CRPが軽度~中等度上昇することがあります。
抗体検査で調べることもできますが、疑陽性(間違って陽性と判断されること)が多く、抗体自体は過去の感染でも数か月陽性のままであり治療に役立てるのはやや難しいです。
レントゲン検査
スリガラス様間質性陰影と言われるようなもやがかかった様な様子やその他、多彩な画像になることがあります。
抗原の検出
咽頭ぬぐい液から抗原を検出することができます。
15分ほどで結果が出ますが感度が低いこと(実際は感染してても陰性になってしまうこと)が問題と言われています。(東京都感染症センター)
抗体検査
培養検査
治療
抗菌薬(抗生物質)による治療が必要になります。
マイコプラズマはやや特殊な細菌で効果があるのは一部のもの(マクロライド系、テトラサイクリン系、キノロン系など)に限られます。
また、近年では耐性菌も増加してきているため、治療効果が悪い場合には系統を変えて治療していく必要があります。
重症化した場合には入院での治療が必要になることもあります。
予防
感染の経路はかぜやインフルエンザと同様ですので、普段から手洗いをすることが重要になります。
患者の咳や唾液から感染しますので、咳症状の人がいる場合にはマスクを着用することをお勧めします。
まとめ
- 持続する咳
- 発熱
- 周囲でのマイコプラズマの流行状況